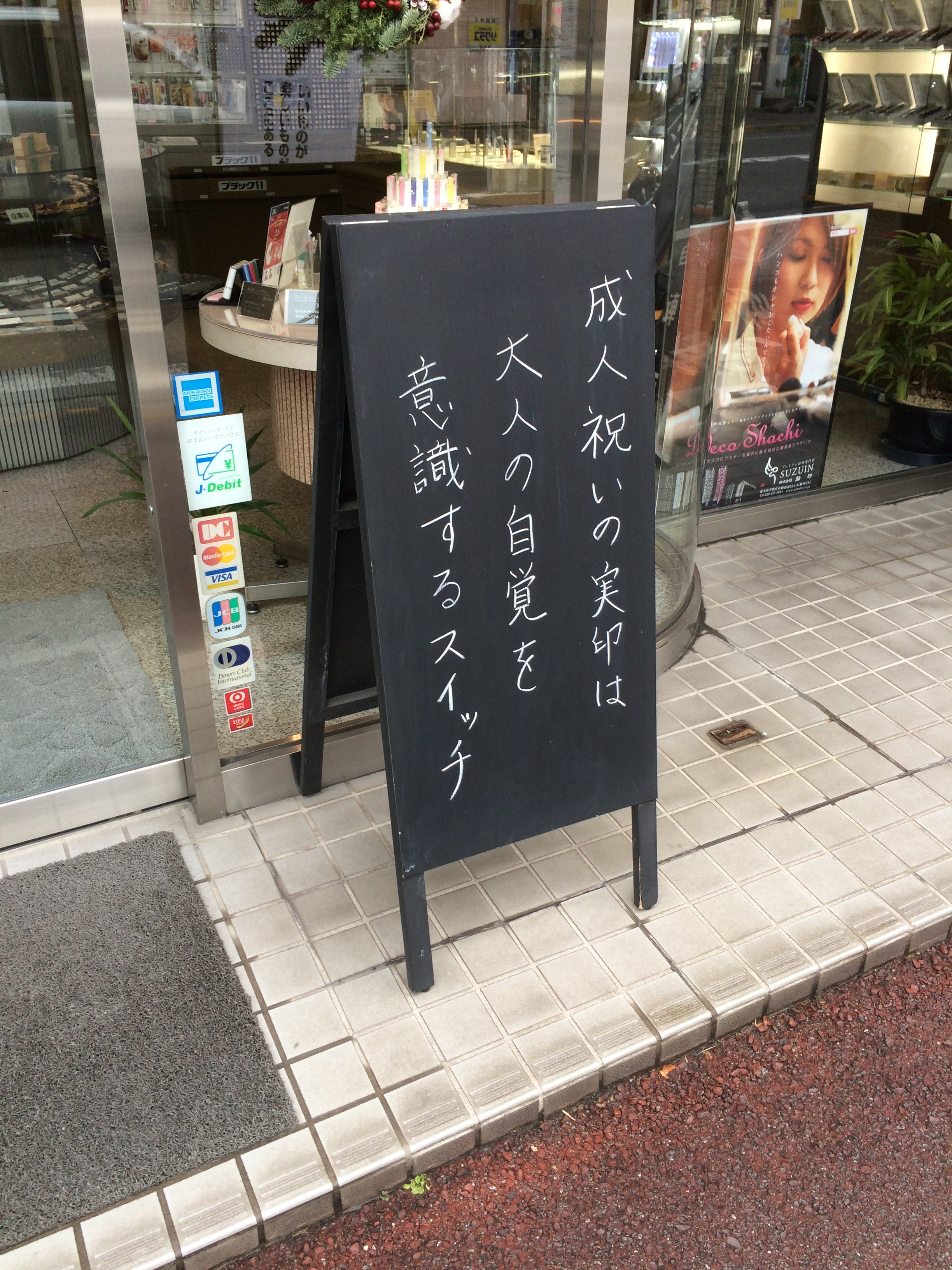明けましておめでとうございます!
いよいよ令和の幕開け。
通常ですとお休みの本日お店を開けたのは、そんな何かがはじまる感も1つの理由なのかもしれません。
令和の意味
すでにあちこちで言われていますけど、私も文字に関わる仕事でもありますので、手元の辞書、白川静さんの字解を開き「令和」の意味などを調べてみました。
令
象形。深い儀礼用の帽子を被り、跪いて神託(神のお告げ)を受ける人の形。神の神託として与えられるものを令といい、「神のおつげ、おつげ」の意味となり、天子など上位の人の「みことのり、いいつけ、いいつける」の意味となる。甲骨文字、金文では令を命の意味に用いており、令が命のもとの字である。令は神のお告げを受け、神意に従うことから、「よい、りっぱ」の意味となり、また使役の「シム」の意味にも用いて、命と分けて使うようになった。
白川静 字解より
和
会意。禾(か)と口とを組み合わせた形。禾は軍門に立てる標識の木の形。禾を並べた禾禾(れき)は軍門の形である。口は口(さい)で、神への祈りの文字である祝詞(のりと)を入れる器の形。口をおいた軍門の前で誓約して媾和(こうわ)する(戦争をやめ、平和な状態にもどす)ことを和といい、「やわらぐ、やわらげる、なごむ、なごやか」の意味となる。[中庸、第一章]に「和なる者は、天下の達道なり」とあって、和は最高の徳行を示す語とされている。
白川静 字解より
解釈は人それぞれかと思いますが、私なりにわかりやすい部分を繋げると「良く和む」そんな感じになりますかね?
独身時代にはピンとこなかったかもしれませんけど、子供たちにはそうあってもらいたいような気がしますよね。
喧嘩ばっかしてないで、みんなと仲良くしなよって。
だからそんな解釈で良いのかなって思います。
最後に
振り返りますと昭和は祖父の時代。平成は父の時代でした。
正確にはそれぞれが最も輝いていたのがその時代。
私も社長になってもうちょっとで10年。
なんとなく馴染んできた感じですけど、創業100年という目標に向けて、良く和みながら進んでいきたいと思います。
それにしてもお正月じゃないですけど、何かがはじまる感はワクワクしますね!
令和もどうぞ宜しくお願い致します。