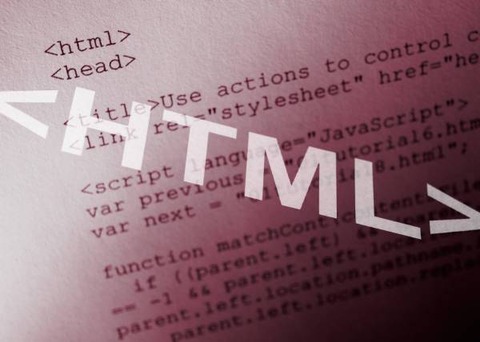実印は一生ものと言われます。
では、その一生が終わった時、つまりお亡くなりになられた後の効力や取り扱い方法はどうしたらいいのか?
残されたご家族は知っておかなかればいけないことですので、ご確認ください。
2015年1月31日に書いたブログですが、2021年5月31日にリライトしました。
ご本人が亡くなってしまった後の実印の効力

まず結論から申し上げます。
本人が亡くなった場合、死亡届の提出と共に実印登録も自動的に抹消されるため、効力はなくなります。
また自動的に抹消されますから、印鑑登録の廃止手続きは不要になります。
つまり亡くなった時点で、実印をしての役目を終えるんですね。
では亡くなった方が有していた権利は、その後どのように移っていくのでしょうか?
亡くなった方の実印がないと困ることがあるのでしょうか?
ご本人が亡くなってしまった後の、権利移行と実印
車の所有権
亡くなった場合、車は遺産になりますから、相続の対象になります。
またそれを機に売却する場合も、相続された方に権利が移行します。
その他、動産・不動産も同じ考えですね。
つまり車の売買に関しても、亡くなった方の実印ではなく、相続された方の実印が必要になります。
保険の契約
保険はご本人が亡くなった場合、受取人がいます。
ということは、保険の契約も亡くなったと同時に、契約が終了になるんですね。
多額の保険金を受け取る場合は実印が必要ですが、この場合は受取人の実印が必要ではありますが、亡くなった方の実印は必要ありません。
また保険は契約内容によって異なりますので、詳しくは保険会社にご確認ください。
預金の引き出し
亡くなった後に、遺産分割協議書に相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
遺産を受け取る、もしくは受け取らない意思の担保ですから、実印は必ず必要です。
ただしここでの実印も相続人のものになりますので、亡くなった方の実印がないと手続きができないという事はありません。
こちらも相続に関して色々はケースがございますので、詳しくは司法書士さんにご確認ください。
ご本人が亡くなってしまった後の実印や印鑑登録カードの取り扱い方法
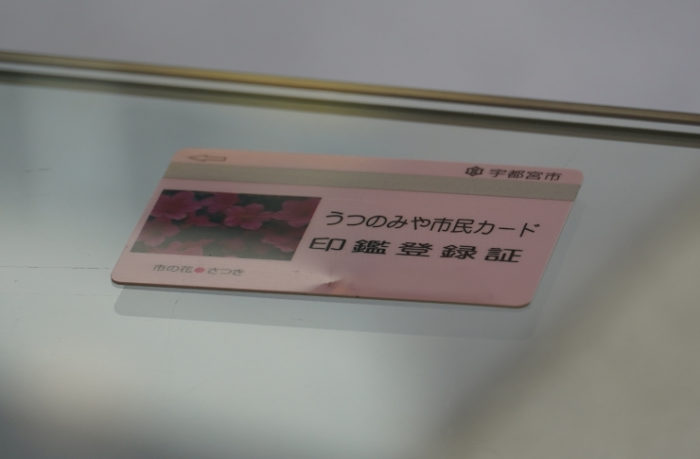
ここまでで、亡くなられた後に実印が必要ないことは分かりました。
でも疑問が浮かびますね。
その実印と印鑑登録カードの扱いはどうしたらいいのか?
亡くなった方の実印の取り扱い方法(1
A:ご自身で処分する
特に決まりがあるわけではありませんが大切な実印ですから、可能であればどんど焼きなどで、大切に祀っていただく方法をお勧めします。
亡くなった方の実印の取り扱い方法(2
A:近くの印章店で預かってもらう
鈴印も会員になっている「公益社団法人全日本印章業協会」加盟店では、印章祈願祭という活動を行っています。
毎年、10月1日「印章の日」を記念して9月の最終日曜日に京都下鴨神社にて開催いたします。
永年お使いになった、古印章(役目を終えた古い印象)を本殿にてご祈祷いたします。
全国から集まった古印章は印納社にて埋納式が執り行われお社に納められます。
各店舗によって多少対応が異なる場合もありますが、お近くの加盟店にご相談いただくか、もしくは鈴印までお送りください。
鈴印では無料で対応させていただいております。
亡くなった方の実印の取り扱い方法(3
A:彫り直して使う
水牛やチタン、そして象牙などは彫り直して使うことができます。
ただし注意点もありますので、詳しくは以下のブログをご覧ください。
亡くなった方の印鑑カードの取り扱い方法
A:役所の市民課に届ける、もしくはご自身で破棄する。
こちらは特に気を遣う必要はなさそうですので、少なくともハサミやシュレッダーで裁断するなどをしつつ処分してください。
最後に
簡単にまとめますと、ご本人様が亡くなった場合の実印は
- 死亡届を出した時点で抹消される
- その後の契約の引き継ぎは、相続人の実印で行う
- 材料によって彫り直して継承することができる
となります。
私も何度か経験がありますが、いざという時は慌ててしまいますので、事前になんとなく頭の片隅に入れておくといいかもしれません。
そして亡くなられた後にその方の実印は、絶対に捺さないでください。
文書偽造に罪に問われてしまいますので、くれぐれもご注意ください。
今回のブログは、入り口程度の内容になります。
詳しくは保険会社や司法書士に、また金融機関によっても取り扱いが異なるので、詳しくは契約先にご確認ください。